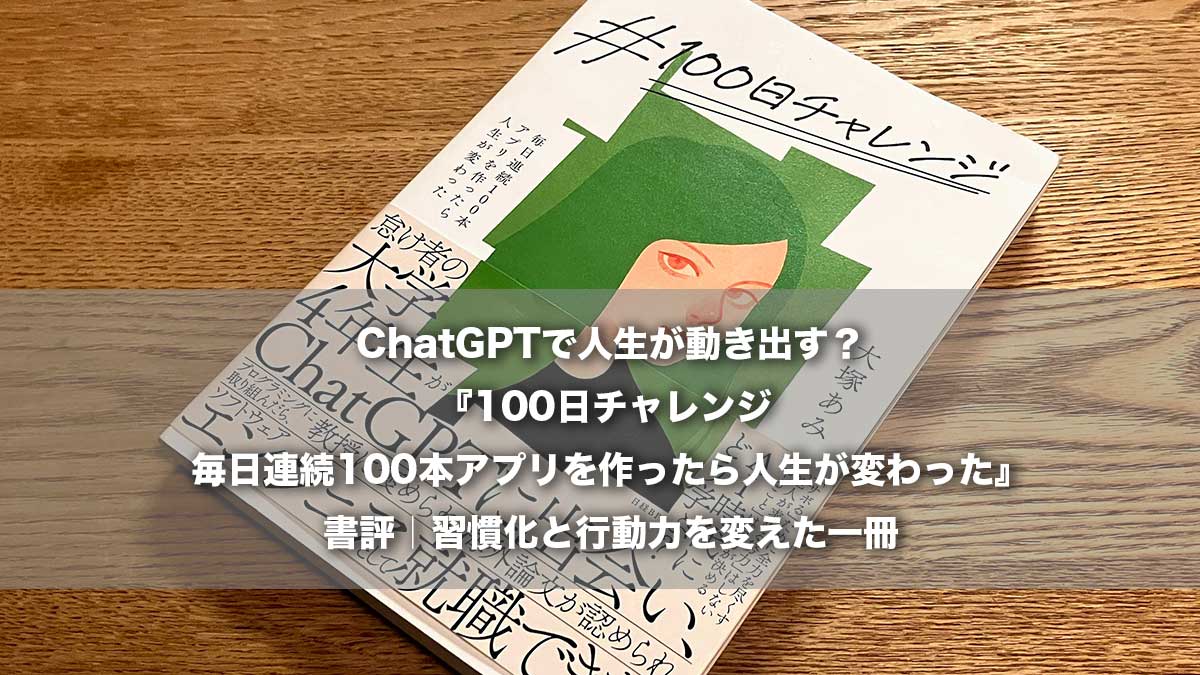ある日、スマホで何気なくスクロールしていた時に、ふと目に止まった記事がありました。タイトルは『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』。特に強く探していたわけでもなく、たまたま見つけたその紹介文が、自分の中に残っていた「ChatGPTをもっと活用したい」という思いを刺激しました。
私はプログラマーではありません。ただ、ここ最近ChatGPTに興味を持ち、使ってはいるものの、正直言って「使いこなしている」とは言いがたい状態でした。そんな中で出会ったのが、本書の著者・大塚あみさんが“さぼるために全力を尽くした”というユニークな姿勢でした。
一般的に「さぼる」という言葉には、怠ける、努力しないというネガティブな印象があります。しかし彼女の場合、それは効率化を徹底的に突き詰め、自分の時間を最大限確保するための戦略的な行動。むしろ現代的な働き方やタスク管理の考え方に近く、「これはまさに、自分が仕事で求められていることと地続きではないか」と直感的に感じました。
プログラマーではない自分にとっても、この本はとても刺さりました。最初は「さぼるため」という動機から始めた取り組みが、ChatGPTと向き合い、失敗し、必要な知識を調べ、学び、そして応用していく中で、「自分がどう動くか」で結果が変わるプロセスの積み重ねへと変わっていく。その様子は、AIを使いこなすために一番大事なのは「指示を出す力=思考力」だということを、自然と教えてくれました。
そして本書を通じて感じたのは、「挑戦は誰にでもできる」ということ。
不純な動機だったかもしれないけれど、それでも毎日少しずつ積み重ねていくうちに、彼女の人生は静かに、でも確実に違う方向へと動き出していきます。大きな夢や目標でなくても、小さな行動の連続が人を変える——そう強く感じさせられました。
実際、私自身もこの本に背中を押されるように、ブログを土日を除いて毎日更新する習慣を続けています。始めた当初に比べて、「何を書こうか」「どう書けば伝わるか」といった構成や表現が、明らかにスムーズに出てくるようになってきました。もちろん文章作成ではChatGPTに相談しながら書いていますが、継続する中で得られる思考の整理力や、アウトプットの精度向上は実感しています。
本記事では、そんな自分の体験も交えながら、
- 本書の概要
- 印象的だった点
- 自分に起きた気づき
- どんな人におすすめか
といった内容をご紹介していきます。もし今、「何か始めたいけど、続けられる自信がない」と感じている方がいれば、きっとヒントが見つかるはずです。
本の概要と著者について
『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』(著:大塚あみ)は、Z世代の大学4年生である著者が、ChatGPTとの出会いをきっかけに「毎日1本、100日間連続でアプリを作る」という挑戦を記録したエッセイです。
もともと「サボることに全力を尽くす」タイプだった著者は、大学の授業でChatGPTに出会い、宿題を効率よく終わらせるためにAIの活用をスタート。しかしその便利さと可能性に魅了され、気がつけばプログラミングにも応用し始めていました。
「ちょっとした暇つぶし」だったはずの行動は、やがて#100日チャレンジという連続投稿のかたちで本格的なプロジェクトへと発展。著者は毎日X(旧Twitter)にアプリ作品を投稿しながら、AIとの対話と自分自身との格闘を繰り返していきます。
この挑戦は、単なる奮闘記録にとどまらず、
- オブジェクト指向やデザインパターンの実践的習得
- 教授からの高評価
- 海外論文の採択
- ソフトウェアエンジニアとしての就職
といった具体的な成果へとつながり、著者の人生そのものが大きく動き出す過程が描かれています。
特徴的なのは、「遊び」や「好奇心」から始まった取り組みが、試行錯誤を通じて、実践的なスキルや自己変革へとつながっていく点です。
生成AI時代の新しい学び方・働き方、そして“さぼる”というキーワードをポジティブに捉えなおす思考の転換を、リアルな言葉で伝えてくれる一冊となっています。
印象に残った内容・キーワード
『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』の中で特に心に残ったのは、“サボる”という言葉に込められた価値観の転換です。
著者・大塚あみさんは、「いかにサボるか」を突き詰めることで、むしろ行動の質を高め、日常を前に進める力を得ていきます。多くの人がネガティブに捉えがちな“サボり”を、「どうすれば少ない労力で最大の成果を出せるか」という視点に変換していく姿勢は、働き方そのものに対する新しいヒントにもなりました。
中でも印象的だったのは、以下の3つの要素です。
① ChatGPTは“使えば便利”ではなく、“使いこなすには思考力が要る”ツール
本書を通して改めて感じたのは、ChatGPTは魔法のようなツールではなく、自分がどれだけ明確に考え、問いを立てられるかによって成果が大きく変わるということです。
著者も最初は「宿題をラクにするため」に使い始めたものの、次第に「思った通りに動かすには、こちらの指示の出し方が重要」だと気づいていきます。この過程はまさに“対話型AIとの共同作業”であり、読みながら「自分ももっとChatGPTを活用できるようになりたい」と感じました。
② 習慣化と継続がもたらす、目に見えない変化
著者は当初、プログラミング学習の進捗をX(旧Twitter)に毎日投稿し、フォロワーに見てもらうことで強制的に継続できる環境をつくろうとしていました。モチベーション維持に加え、自身の技術力を証明する手段にもなるのではという意図もあったようです。
やがてこの継続は、「やらなければ」から「もっとやりたい」へと意識が変化。24日目には教授から論文発表の提案を受け、取り組みが学業やキャリアとつながる転機となります。日々の努力が未来への投資という実感に変わっていく過程がとても印象的でした。
このように、興味と成果が重なり合うことで、継続は義務から主体的な行動へと自然に変わっていく。著者の経験からは、無理なく続けるための現実的なヒントが多く得られました。
私自身もブログ更新を続ける中で、少しずつ書く力や構成力が身につきつつある実感があります。やはり続けて初めて見える成長があるという点で、強く共感できました。
③ 始まりは軽くていい。不純な動機でも、未来は動き出す
著者がこのチャレンジを始めたのは、「暇つぶし」「ChatGPTが面白い」「サボりたい」という、ごく自然でゆるい動機からでした。それでも、行動を続けていく中で、プログラミングの知識を学び、英語文献を読み、就職にまでつながっていく。
最初の一歩の“純度”は関係ない。大事なのは踏み出すことと、続けること。
そんなメッセージを、押しつけがましくなく、でも確かに受け取ることができました。
本を読んで自分に起きた変化
この本を読んで、「自分にも何かを続けられるかもしれない」という感覚が芽生えました。特に印象的だったのは、著者が完璧を求めず、とにかく毎日アウトプットを重ねていく姿勢です。試行錯誤しながら、ChatGPTをうまく使う方法を模索する過程には、AIを使いこなしたいという自分の関心とも重なる部分が多く、強く共感しました。
私自身、現在ブログの平日更新を続けており、最初のころに比べて文章構成や思考の整理がスムーズになってきた実感があります。もちろん、ChatGPTのサポートも活用していますが、継続しているからこそ見えてくる改善点や手応えがあるという点では、著者の体験と重なる部分が多くありました。
この本は、“始めるハードルの低さ”と“続けることで得られる変化”を、等身大の言葉で伝えてくれます。読後には、少しだけでも行動を変えてみたくなる——そんな前向きな気持ちにさせられました。
こんな人におすすめ
『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』は、次のような方におすすめです:
- ChatGPTを活用して何か始めてみたい人
- 学びやスキルアップに興味があるけれど、継続に不安がある人
- 「やりたいことはあるけど一歩踏み出せない」と感じている人
- AI時代における新しい成長のかたちを知りたい人
特に、「行動したいけど完璧を求めてしまって動けない」という方にとっては、著者の等身大の試行錯誤が強く背中を押してくれるはずです。
まとめ & 購入リンク
『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』は、ChatGPTという新しいツールとの出会いから始まった、自分の可能性を広げる“100日の旅”を描いたリアルな記録です。
完璧でなくてもいい、スモールスタートでいい——まず始めて、続けてみる。
その先に見える変化や成長の実感が、読み手にも伝わってきます。
私自身、読後には「自分もこのまま続けていこう」という気持ちを新たにすることができました。AI活用や継続、習慣化に興味のある方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。